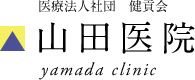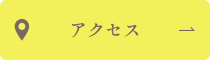いぼ除去
ウイルス性?加齢性?
いぼの種類と違い
 イボができる疾患として、以下のものが挙げられます。
イボができる疾患として、以下のものが挙げられます。
ウイルス性のいぼ
尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)
尋常性疣贅は、手のひらや足の裏にできやすいザラついたイボで、ヒトパピローマウイルスによる感染が原因です。
青年扁平疣贅(へんぺいゆうぜい)
おでこや手の甲に多発しやすい平らなイボで、ヒトパピローマウイルスの感染によって生じます。
尖圭コンジローマ
ヒトパピローマウイルスによる性感染症の1つで、亀頭や外陰部、肛門まわりなどに先端が尖った乳頭状またはカリフラワー状のイボが現れます。
ミルメシア
噴火口のように中央が窪んだドーム状のイボで、手のひらや足の裏に生じ、魚の目と間違われることがあります。
伝染性軟属腫(水いぼ)
主に子供にみられるツヤのある粒状のイボで、痒みを伴い、掻き壊すことで周囲に広がることがあります。
紫外線・加齢によるいぼ
老人性疣贅(脂漏性角化症)
60歳以上の方に多くみられる茶色〜褐色の盛り上がったイボで、加齢や紫外線による皮膚へのダメージが原因とされています。
軟性線維腫(スキンタッグ・首いぼ)
摩擦や加齢、紫外線などの刺激が原因となり、皮膚の薄い首まわりなどにできる小さな突起です。中年以降の方に多く見られます。
アクロコルドン(首いぼ、脇いぼ、胸いぼ)
首や脇、胸周りに生じる小さな突起状のイボで、摩擦の刺激が発症要因とされ、30代以降に多く見られます。
いぼの原因
イボは主にヒトパピローマウイルスによる感染が原因とされ、感染はヒトとの直接的な接触だけでなく、プールや浴場の足拭きマット、スリッパなどを介して間接的にも広がることがあります。
ウイルス
ヒトパピローマウイルス(HPV)
イボの発生に加え、性感染症の原因にもなります。子宮頸がんや尖圭コンジローマの原因として知られています。
伝染性軟属腫ウイルス
水いぼができる原因です。皮膚内でウイルスが増殖して現れ、掻き壊すことで広がったり、タオルなどを介して家族間で感染することがありますので注意が必要です。
紫外線・加齢・摩擦
老人性イボの場合は加齢や紫外線、摩擦などの影響で発症しやすく、特に頭皮・顔・首まわりに多く見られます。
いぼの治療法
炭酸ガスレーザーによる焼却
局所麻酔を行った上で蒸発させるように、イボを削る治療です。出血がなく、傷跡も目立ちにくい利点があります。
ピンセットによる除去
水いぼには、ピンセットによる摘除法が行われます。数日間は傷が残ることがありますが、徐々に目立たなくなっていきます。
スピール膏(サリチル酸絆創膏)
足裏など皮膚の厚い部分のイボでは、スピール膏(サリチル酸絆創膏)を用いることで皮膚を柔らかくして脱落を促すことが可能です。
イミキモドクリーム外用薬
尖圭コンジローマの治療に用いる外用薬です。1日おきに塗り、塗布した日の翌日にシャワーなどで洗い流してください。
漢方薬(ヨクイニン)
ヨクイニン(ハトムギ抽出成分)は、免疫を高めてイボの改善を目指すのに有効な漢方薬です。
ほくろ除去
なぜほくろが増える?原因とできやすい体質・生活習慣とは

紫外線
紫外線を多く浴びることで、メラニン色素の生成が活発になり、ほくろが増えるリスクが高まります。紫外線は5月から8月にかけて最も強くなりますが、季節や天候に関係なく、室内にも届きますので、年間を通じた紫外線対策が重要です。
生活習慣の乱れ
食生活の乱れや睡眠不足によって、肌のターンオーバーが正常に働かなくなると、メラノサイトが排出されずに蓄積し、しみやほくろを招きます。
ホルモンバランスの乱れ
女性の場合、月経時に分泌される黄体ホルモン(プロゲステロン)の作用により、ほくろが増えることがあります。
皮膚への刺激
日々のメイクや摩擦などによる皮膚への刺激も、メラノサイトの活性化を促し、ほくろができやすくなる要因となります。
ほくろの種類
Unna(ウンナ)母斑
胸・お腹・背中など体幹に多くみられる柔らかい黒〜茶褐色のしこりで、直径1cm程度の大きさです。
Miescher(ミーシャー)母斑
顔や頭皮によく見られ、膨らみがあり毛が生えていることもあります。年齢とともに色が薄くなる傾向があります。
Spitz(スピッツ)母斑
赤〜黒色をしており若年層に多く、急速に大きくなることがあり、皮膚がんとの鑑別が必要になることがあります。
Clark(クラーク)母斑
体幹や四肢にできやすく、楕円形でほぼ平坦、直径1cm以下のことが多いです。色調は中央が濃く、外側に向かって薄くなる傾向があります。
ほくろと見た目が
似ている病気
ほくろに似た皮膚疾患には、早期の鑑別が必要なものもあります。
皮膚線維腫
皮膚線維腫は、虫刺されや外傷をきっかけに腕や足にできる黒〜褐色のしこりです。
神経線維腫
肌色でドーム状に盛り上がったいぼです。単発の場合が多いですが、複数ある場合は遺伝性の疾患(神経線維腫症)の可能性もあります。
軟性線維腫
軟性線維腫は首やわきの下など皮膚が薄く摩擦されやすい部位に生じる肌色のいぼ状の突起で、加齢や紫外線などが原因とされています。
脂漏性角化症
加齢と紫外線による皮膚ダメージの蓄積により生じる、茶色く盛り上がったしみです。特に顔や首まわりに多くみられます。
基底細胞がん
艶のある小さな皮膚の盛り上がりとして現れ、徐々に大きくなって血管が見えたり出血することもあります。ほくろと似ているものも存在するため、拡大鏡(ダーモスコピー)による診察や手術による切除が行われます。
悪性黒色腫
(メラノーマ・皮膚がん)
足の裏などにできることが多く、全身へ転移しやすい皮膚がんです。命に関わる可能性があるため、発見次第、専門医療機関での速やかな治療が必要となります。
ほくろの治療法
切除法
皮膚をなるべく傷つけないよう丁寧に縫合し、時間の経過とともに傷跡は目立ちにくくなります。脂肪層までしっかり取り除くため、再発の可能性が低く、病理検査による確認も可能です。特にケロイド体質の方や、悪性が疑われる場合には適した方法とされています。
炭酸ガスレーザー
ほくろの部分にレーザーを照射して、出血をほとんど伴わず除去できる治療です。切除法と比べて傷跡が小さく済むため、顔などの目立つ部位には向いています。
ただし、取り残しや再発の可能性があるため、複数回の治療が必要になることがあります。