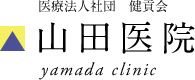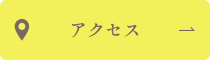生活習慣病
 生活習慣病とは、不規則な食生活、運動不足、喫煙、ストレス過多、および過度のアルコール摂取などが主な原因で起こる疾患です。
生活習慣病とは、不規則な食生活、運動不足、喫煙、ストレス過多、および過度のアルコール摂取などが主な原因で起こる疾患です。
代表的な生活習慣病と
そのリスク
代表的なものには、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満、動脈硬化があり、これらは単独でも複合しても進行する可能性があります。
変わりゆく日本の
生活リズムと健康への影響
日本では戦後の食の欧米化により、脂肪・塩分の多い食事が増え、野菜や果物の摂取が減少しています。加えて、都市化やデジタル機器の普及が運動不足を助長し、健康リスクを高めています。
ストレス社会・デジタル生活がもたらす健康リスク
忙しい現代社会では、規則正しい生活の継続が難しく、インターネット・スマホの利用習慣も健康への悪影響につながる要因となっています。生活リズムの見直しが、予防と改善の鍵となります。
糖尿病
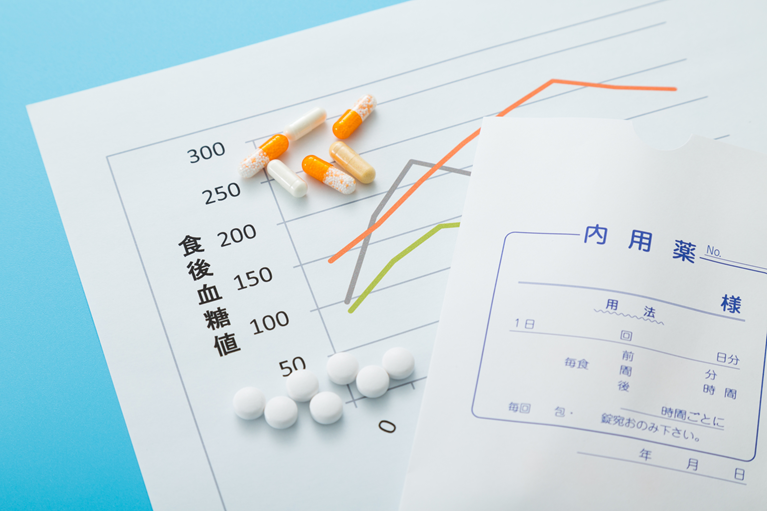 糖尿病は、血糖値が持続的に上昇する代謝疾患で、その原因はインスリンの分泌や作用に問題があることです。
糖尿病は、血糖値が持続的に上昇する代謝疾患で、その原因はインスリンの分泌や作用に問題があることです。
糖尿病の原因
1型糖尿病の場合は、自己免疫反応によって膵臓のβ細胞が攻撃され、インスリンが生成されなくなることです。2型糖尿病は、遺伝的要因や、食習慣の乱れ、運動不足、肥満、ストレスなどの生活習慣が主な原因とされています。また、年齢や高血圧もリスクを増大させます。
また、妊娠糖尿病は、妊娠中のホルモンの影響により、一時的にインスリンの効果が低下することで発症します。
糖尿病の症状
初期段階での糖尿病は、特に自覚症状がないことが一般的ですが、進行すると頻尿、喉が渇く、体重減少、疲労感などの症状が出ます。
糖尿病の検査・診断
- 空腹時血糖値 126mg/dl以上
- 随時血糖値 200mg/dl以上
- 経口ブドウ糖負荷試験2時間値 200mg/dl以上
- ヘモグロビンA1c 6.5%以上
空腹時血糖値
10時間以上食事をとっていない時の血糖値です。
随時血糖値
食後以降の時間に関わらず測定された血糖値です。
経口ブドウ糖負荷試験
2時間値
糖尿病の診断には、空腹時に75gのブドウ糖を摂取し、2時間後の血糖値を測定する検査が用いられます。この検査で「糖尿病型」と判定され、その結果が別の日にも確認されると「糖尿病」と診断されます。また、以下の条件のいずれかを満たす場合、1回の検査でも糖尿病と診断されることがあります。
- ヘモグロビンA1cが6.5%以上で、血糖値が糖尿病型に該当する
- 血糖値が糖尿病型で、喉の渇き・多飲・多尿・体重減少などの症状がある
- 血糖値が糖尿病型で、糖尿病性網膜症が認められる
糖尿病の治療
1型糖尿病では、インスリン療法が不可欠であり、定期的な注射が必要です。
2型糖尿病の場合、主に糖質やカロリーの制限などの食事療法、運動療法、薬物療法が用いられます。
内服薬
以下の内服薬が使用されます。
ビグアナイド系
肝臓が糖を生成する機能を抑制したり、血液から筋肉に糖を取り込む量を増やしたりする効果があります。
グリミン系
インスリンの分泌を促し、膵臓β細胞を保護する働きがあります。さらに、肝臓や骨格筋での糖代謝を改善し、インスリン抵抗性を軽減する効果も期待できます。
チアゾリジン薬
インスリンの効きを改善し、組織(筋肉、脂肪)での糖の取り込みや糖利用を改善します。また肝臓での糖放出を抑えることで血糖値を改善する効果もあります。
DPP-4阻害剤
膵臓内で分泌されるインスリンを増やす働きを持つ「インクレチン」というホルモンの働きを活性化させる薬です。インクレチンは食後に分泌され、その結果、血糖をコントロールする働きが促されます。
GLP-1受容体作動薬
GLP-1はインクレチン(食事を摂ることで分泌され、インスリンの分泌を促進し、血糖を上昇させるグルカゴンというホルモンの放出を抑制する物質)の一種です。食欲が落ちて体重が減る効果が認められており、肥満症に対しても使われています。
GIP/GLP-1受容体作動薬
インクレチンとして主なものに、GLP-1の他にGIP(glucose-dependent insulinotropic polypeptide)があります。この薬剤は、GIPとGLP-1の二つの受容体に作用します。そのため、GIP/GLP-1受容体作動薬はGLP-1受容体作動薬よりも体重減少効果が強いと言われています。
SGLT2阻害剤
腎臓の尿細管で血液中に糖が取り込まれるのを防ぐ作用があります。近年では心不全や慢性腎臓病の治療薬としても使用されるようになっています。
スルホニル尿素薬
血糖降下薬の中でも最も古い系統の薬剤です。膵臓でのインスリン分泌を促進する薬剤で、作用が強力なため低血糖に気を付ける必要があります。
即効型インスリン分泌促進薬
グリニド系とも呼ばれます。即効性があり、短期間に膵臓からのインスリン分泌を促進します。すぐに効果を発揮して、すぐに効果がなくなります。そのため、食後の高血糖を防ぐ目的で食直前に内服してもらいます。
α-グルコシダーゼ阻害薬
主に小腸での糖の消化や吸収を抑制する作用のある薬です。食事に含まれている糖質の消化を妨げることで食後の血糖上昇を抑えます。
糖尿病の予防・改善
2型糖尿病は、肥満や運動不足が主な原因となることが多いので、適切な体重を維持することが非常に重要です。脂肪や糖質の摂取を控え、野菜や食物繊維を積極的に摂取することが勧められています。
さらに、定期的な運動によって、血糖値の急上昇を防ぐだけでなく、インスリンの効果を向上させることができます。健康診断による血糖値のモニタリングを定期的に行い、早期に問題を発見することが極めて重要です。
高血圧症
 高血圧とは、血液が流れる際に血管へかかる圧力が慢性的に高い状態を指す疾患です。血圧は心臓が収縮する時の「収縮期血圧」と、拡張する時の「拡張期血圧」の2つで表されます。
高血圧とは、血液が流れる際に血管へかかる圧力が慢性的に高い状態を指す疾患です。血圧は心臓が収縮する時の「収縮期血圧」と、拡張する時の「拡張期血圧」の2つで表されます。
高血圧症の原因
高血圧で多いのが「本態性高血圧」で、遺伝や年齢、食生活、運動不足、そしてストレスが関連しています。 また、10人に1人程度が「二次性高血圧」とされ、腎臓やホルモンなどの疾患によって引き起こされます。
高血圧症の症状
高血圧症の症状は、ほとんどが自覚しにくいとされていますが、高血圧が長期間継続したり、急激に血圧が上昇したりすると、頭痛、めまい、耳鳴り、動悸、そして視力の障害などの症状が出現することがあります。
高血圧症の診断・治療
生活習慣の改善としては減塩、適度な運動、禁煙、節酒、ストレスの軽減などがあり、肥満がある場合には減量も有効です。血圧の目標値ですが、75歳未満では診察時130/80mmHg未満(家庭では125/75mmHg未満)、75歳以上では診察時140/90mmHg未満(家庭では135/85mmHg未満)を目安にします。薬物療法では、血圧のコントロールを補助するための降圧薬が使用されます。
カルシウム拮抗薬
血管を広げ、血圧を下げる作用があります。
アンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)、アンギオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬
ARBはアンギオテンシンIIという血管収縮作用を持つホルモンの効果を減少させ、血管を広げる作用があります。
一方、ACE阻害剤は、ACEというアンギオテンシンIIを生成する酵素を阻害し、血管を広げる効果も持っており、それに加えて、心臓や腎臓を保護する働きもあります。
アンギオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬(ARNI)
血管を拡張するホルモンであるネプリライシンや、ナトリウム利尿ペプチドの心臓保護作用を阻害する作用があります。
利尿薬(サイアザイト系またはサイアザイド類似利尿剤、ループ利尿薬)
腎臓に作用して水分や塩分を尿として排出し、血圧が下がる効果があります。特に塩分摂取過多の方に有効です。
ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
アルドステロンというホルモンの作用を抑える薬剤です。アルドステロンは、体内の水分や塩分を保持する働きがあります。
β遮断薬
心臓の筋肉に作用して、交感神経のβ1受容体をブロックすることで、心拍数を下げて心臓の収縮を調整します。
α遮断薬
交感神経のα1受容体をブロックし、血管を広げて血圧を下げます。
高血圧症の予防・改善
まずは過度の塩分摂取を控え、野菜や果物が豊富なバランスの良い食事を意識しましょう。さらに、適度な運動は血圧安定に有効です。喫煙や過度な飲酒を避けることも、予防に大いに役立ちます。
脂質異常症
 脂質異常症は、血液中の脂質(LDLコレステロール、中性脂肪など)が過剰になったり、HDLコレステロールが不足したりすることで、動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳卒中などのリスクが高まる疾患です。多くの場合症状がなく、早期発見には定期的な血液検査が重要です。
脂質異常症は、血液中の脂質(LDLコレステロール、中性脂肪など)が過剰になったり、HDLコレステロールが不足したりすることで、動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳卒中などのリスクが高まる疾患です。多くの場合症状がなく、早期発見には定期的な血液検査が重要です。
脂質異常症の原因
主な原因は遺伝的体質と生活習慣によるものです。遺伝的には家族性高コレステロール血症などが関係し、生活習慣では高脂肪・高糖質な食事、運動不足、肥満、喫煙、過度の飲酒が要因となります。
脂質異常症の症状
初期には症状がほとんどないため「サイレントキラー」と呼ばれ、知らぬ間に動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳卒中などの重大な疾患につながる可能性があります。稀に、瞼やアキレス腱などに黄色腫(コレステロールが沈着したこぶ)が現れることもあります。
脂質異常症の診断・治療
脂質異常症の治療は、食事や運動などの生活習慣の改善と薬の併用が基本です。食事では脂肪や糖質を控え、魚・野菜・食物繊維を多く摂ることが推奨され、飽和脂肪酸の多い食品は避けましょう。運動の習慣化、禁煙、節酒も重要です。薬物療法ではスタチンやフィブラート系の薬が用いられ、LDLコレステロールや中性脂肪の低下を目指します。
| 項目 | LDLコレステロールの目標値 |
|---|---|
| 家族性コレステロール血症の方 | 100mg/dl未満 |
| 「冠動脈疾患(狭心症や心筋梗塞など)」や 「アテローム血栓性脳梗塞」の既往がある方 | 100mg/dl未満 |
| 冠動脈疾患又はアテローム血栓性脳梗塞に加え、「急性冠症候群」、 「家族性高コレステロール血症」、「糖尿病」のいずれかがある方、 「冠動脈疾患」+「アテローム血栓性脳梗塞」のある方 | 70mg/dl未満 |
| 「糖尿病」、「慢性腎臓病」、「末梢動脈疾患」のいずれかがある方 | 120mg/dl未満 |
| 糖尿病に加え、「網膜症・腎症・神経障害」を合併していたり、 「末梢動脈疾患」、「喫煙」のいずれかかがある方 | 100mg/dl未満 |
脂質異常症で使用する薬剤
スタチン系
肝臓でのコレステロール合成を抑制し、LDLコレステロールを効果的に低下させます。効果の強さにより「ストロングスタチン」と「スタンダードスタチン」に分類されます。
フィブラート系
肝臓でのコレステロールおよび中性脂肪の合成を抑えると同時に、中性脂肪の分解を促進し、血中の中性脂肪値を下げる作用があります。
小腸コレステロールトランスポーター阻害剤
小腸でのコレステロールの吸収を抑え、血中のコレステロール値を下げる作用があります。
イコサペント酸エチル(EPA)製剤、オメガ-3脂肪酸エチル(EPA + DHA)
魚油由来の薬剤で、肝臓における中性脂肪の合成を抑え、血中の中性脂肪を低下させる効果があります。
PCSK9阻害薬
血液中のLDLコレステロールの増加に関与する「PCSK9」というタンパク質を抑制することで、肝臓へのコレステロールの取り込みを促進し、血中濃度を低下させる新薬です。
脂質異常症の予防・改善
食事と運動の見直しが重要です。飽和脂肪酸の多い食品(例:肉類やバター)を控え、魚、大豆、野菜、果物などを積極的に取り入れましょう。週数回の有酸素運動を含む日常的な運動習慣も効果的です。さらに、禁煙、節酒、適正な体重管理を心がけることで予防につながります。
高尿酸血症・痛風
 高尿酸血症とは、血液中の尿酸値が7mg/dLを超えた状態で、プリン体の代謝により生じた尿酸が過剰に蓄積することで発症します。尿酸は本来尿から排出されますが、排出が不十分だと関節に沈着し、激しい痛みを伴う痛風発作の原因になります。さらに尿路結石のリスクや腎機能障害を引き起こす可能性もあります。
高尿酸血症とは、血液中の尿酸値が7mg/dLを超えた状態で、プリン体の代謝により生じた尿酸が過剰に蓄積することで発症します。尿酸は本来尿から排出されますが、排出が不十分だと関節に沈着し、激しい痛みを伴う痛風発作の原因になります。さらに尿路結石のリスクや腎機能障害を引き起こす可能性もあります。
高尿酸血症・痛風の原因
高尿酸血症は、尿酸の産生が増加する場合と排泄が低下する場合の両方で起こります。主な原因としては、食生活(肉・魚介・アルコールなどプリン体の過剰摂取)、肥満、ストレス、遺伝、運動不足、そして腎機能の低下や利尿剤などの薬剤の影響が挙げられます。
高尿酸血症・痛風の症状
高尿酸血症自体には自覚症状がないことも多いですが、尿酸が関節に沈着すると痛風発作が生じます。痛風は関節(足の親指の付け根が最も多いが、膝、肘、手首などにも起こる)に、急激な痛み・腫れ・赤みといった症状として現れ、発作を繰り返すと関節が損傷し慢性化する場合もあります。また、皮下や関節部に「痛風結節」と呼ばれるしこりが形成されることがあります。
高尿酸血症・痛風の治療
食事療法と薬物療法が中心です。プリン体を多く含む食品の摂取を控え、バランスの取れた食生活と適度な運動、体重管理が重要です。薬剤では、尿酸の産生を抑えるタイプと排泄を促進するタイプが用いられます。痛風発作時にはコルヒチンや非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)による対症療法を行います。発作の前兆がある場合にはコルヒチンを使用して予防的に対応することもあります。
高尿酸血症・痛風の予防・改善
予防・改善には、プリン体やアルコールの摂取を控え、こまめな水分摂取や適度な運動習慣によって尿酸の排出を促すことが重要です。