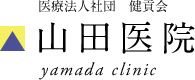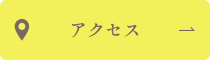- 何度の熱で病院に行くべき?
発熱時の受診の判断基準 - 該当する症状がある方は発熱外来を
ご受診ください - 発熱とともに起こる体の変化や症状
- 発熱外来で行う検査
- 発熱外来受診の流れ
- 発熱外来を受診する際の注意点
- 発熱時に自宅でできる対処法
何度の熱で病院に行くべき?
発熱時の受診の判断基準
 発熱外来では、37.5℃以上の発熱がある方や平熱より1℃以上高く、他にも症状がある方を対象に診療を行います。新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症を正確に診断し、他の病気との判別を目的としています。受診の際は、電話での連絡をお願いします。なお、連絡なしで来院された場合は、院内感染防止のためすぐに対応できないことがあります。
発熱外来では、37.5℃以上の発熱がある方や平熱より1℃以上高く、他にも症状がある方を対象に診療を行います。新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症を正確に診断し、他の病気との判別を目的としています。受診の際は、電話での連絡をお願いします。なお、連絡なしで来院された場合は、院内感染防止のためすぐに対応できないことがあります。
正しく測るための体温計の
使い方と注意点
体温は一般的に腋の下で測定され、最近の電子式体温計では1分ほどで予測値を表示し、約10分で実際の体温が確認できます。予測値でも通常は十分ですが、毎回同じ条件で測定することが大切です。腋が凹んでいる部分の中央部が最も高い温度を示すため、体温計の先端を斜め下からその部分に当て、腋を適度にゆるめてからしっかりと閉じて測定することで、安定した計測が可能になります。
該当する症状がある方は
発熱外来をご受診ください
新型コロナウイルスの感染者との濃厚接触や、ご家族にインフルエンザの診断や高熱の症状がある場合も、発熱外来の受診が推奨されます。

- 発熱がある(37・5℃以上)
- 平熱より体温が1℃以上高い
- 喉の痛み
- 咳
- 痰
- 倦怠感、呼吸困難
- 鼻水
- 鼻詰まり
- 味覚障害、嗅覚障害
- 嘔吐、下痢
発熱とともに起こる
体の変化や症状
体温調整の働きにより、体に特有の症状が現れることがあります。
発熱時
発熱時には、体が体温を調整しようとする反応が現れます。熱が上がる際には寒気や震えを感じ、体が熱を産生しようとします。
熱が続いている時
熱が続くと、体のほてりや心拍・呼吸の増加、関節や筋肉の痛みが現れます。これは感染への抵抗反応です。
熱が下がった時
汗をかくことで体を冷却しようとします。これらは体温調整の自然な働きであり、多くの場合心配のない症状です。
発熱外来で行う検査
発熱外来では、発熱の原因を見極めるために各種検査を実施し、流行性の感染症が疑われる際には、迅速な診断ができる検査により対応します。
新型コロナウイルス検査
新型コロナウイルスが疑われる場合には、症状や接触歴、検査タイミングなどを踏まえて抗原検査を実施します。抗原検査は短時間で結果が得られるため、迅速な診断が必要な場面で使用されます。
インフルエンザ検査
インフルエンザが疑われる場合には、迅速抗原検査を行います。鼻の奥の粘膜から検体を採取して、約15分で結果を確認します。発症後48時間以内の抗ウイルス薬の投与が効果的なため、早期診断が大切です。冬季や流行期には、新型コロナウイルスの検査と併せて行うこともあります。
追加で行うことがある検査
血液液検査
(CRP・白血球数など)
ウイルス感染と細菌感染の判別・炎症の度合いを確認するために行います。CRP(C反応性タンパク)や白血球数などの数値をもとに、重症化や治療方針の判断に役立てます。
尿検査
発熱の原因として尿路感染症など泌尿器系の疾患が疑われる場合には、尿検査を行うことがあります。呼吸器症状が見られない場合には、診断の重要な手がかりとなります。
胸部レントゲン検査
呼吸器感染症が疑われる際は、胸部X線撮影によって肺の状態をチェックします。特に、高齢者や持病のある方で発熱が長引く場合には、早期発見と重症化予防のために行われます。
発熱外来受診の流れ
1ご予約
発熱外来を受診される際は、事前に電話での連絡が必要です。当日受診の場合も電話連絡をお願いします。連絡なしの場合は、院内感染防止のため対応が難しい場合があります。
2問診票
WEB問診票、または来院後に紙での記入をお願いします。
3ご来院
検査精度維持のため受診前15分間は、飲食・喫煙・歯磨きを控えてください。来院時はマスク着用が必要です。
4診察・検査
新型コロナウイルスやインフルエンザの抗原検査結果は院内でお知らせします。
発熱外来を受診する際の注意点
- 遅刻やキャンセル時は、必ずお電話でご連絡ください
- 初診の方は、保険証・医療証をお持ちください
- お薬手帳がある場合はお持ちください
- 院内ではマスク着用をお願いします
- 受診前15分間は、飲食・喫煙・歯磨きを控えてください(検査の精度保持のため)
発熱時に自宅でできる対処法
 以下の方法は、発熱があってもご自宅内でできるセルフケアです。
以下の方法は、発熱があってもご自宅内でできるセルフケアです。
十分な休息
体力を回復させるために、しっかりと体を休めましょう。
こまめな水分補給
脱水予防のため、お茶や水を中心にこまめに水分を摂取。清涼飲料水は控えめにしましょう。
快適な室温維持
室内の温度が暑すぎたり寒すぎたりしないよう調整しましょう。
軽くて通気性の良い服装
体の熱が逃げやすいよう、薄手でかつ風通しの良い衣類を着用しましょう。
適切な解熱剤の使用
医師の指示に従って解熱剤を使いましょう。
※子供にアスピリンは使用しないでください。